


埼玉県民活動総合センターは存続をー山﨑県議一般質問

共生社会の実現へー国際交流協会を視察

川口市内小中学校の日本語教育視察
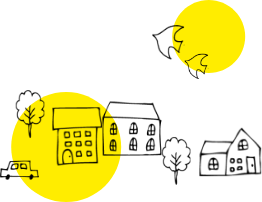

5月19日伊藤はつみ県議、石川けいこ朝霞市議、足立しづ子ふじみ野市議とともに、朝霞市のゾーン30プラスの取り組みについて話を伺いました。

東弁財地区をゾーン30エリアに指定
ゾーン30プラスは、速度が30キロに制限されている道路において、ハンプや狭さくなどの物理的デバイスを設置することで、30キロ以上の速度を出させないようにするものです。
ゾーン30は道路ごとに指定するものですが、朝霞市は駅から近い住宅街で小中学校もある東弁財地区をゾーン30エリアとして設定しました(エリア内の幹線道路、幅員7mから8mの道路は除く)。指定するにあたり、生活道路での道路交通の特性を分析するための国土交通省のビッグデータを活用して、急ブレーキ、速度超過の状況、車両の流入状況などを分析し、課題を洗い出しました。
その上で、2019年から朝霞警察署、地元町内会、学校関係者、PTA、教育委員会、学識経験者、大宮国道事務所の方が参加して計6回のワークショップを開催。ビックデータでの危険箇所も踏まえつつ、ヒヤリ、ハッとした場所など地図に落としたり、どこにどのような物理的デバイスを置くのがいいのかなど話し合いを行いました。
そして2020年に交通安全対策工事が完了しました。
朝霞市は埼玉大学大学院の先生にお願いし、設置前と設置後で車のスピードがどうなっているのかなどのデータを取ってもらい、ハンプや狭さく、グリーンベルト、減速表示、車止めポストの効果について検証も行っています。検証の結果、速度抑制が認められたとの報告もありました。
ワークショップを行ったことで、安全対策の意識が高まる
市の担当の方は「ハンプをつけるには周辺住民の理解が必要だと思います。ワークショップをやったので、苦情はありません。『安全のためには必要だね』とご理解いただいています。ワークショップをすることによって、交通安全への意識が高まったと感じています」と話されていました。
ハンプは大宮国道事務所が貸し出しを行っているそうです。朝霞市でも東弁財地区とは別の場所で実証実験を実施したとのこと。市の担当の方は「最初は振動や騒音を心配して反対していた人も実証実験をしてみると『これはいい』と賛成に回ってくれた」と話していました。
ワークショップを通じて住民の合意を形成していくこと、ハンプを借りて検証してみることができること、専門家にも協力をお願いし、設置前と設置後での効果について検証を行っているのが重要だと感じました。