

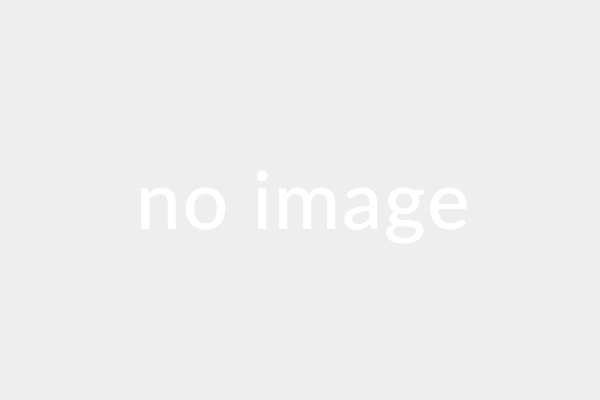
2016年度 政務活動費に関する会計帳簿
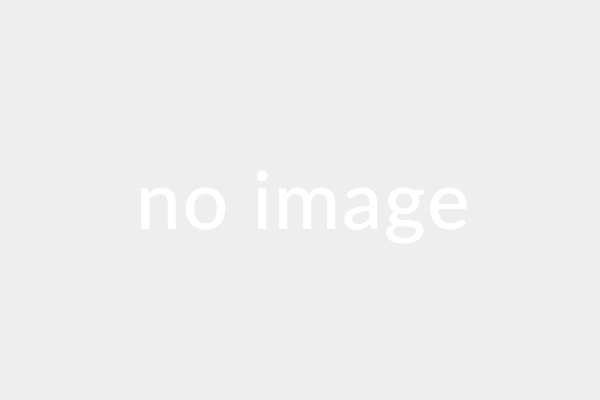
11月10日、山﨑すなお県議は外国にルーツをもつ生徒のための相談や日本語指導を行っている戸田翔陽高校を訪問しました。

外国にルーツを持つ生徒のための多文化共生室
戸田翔陽高校は単位制、定時制の高校です。生徒たちは1部、2部、3部と別れています。戸田翔陽高校では外国にルーツを持つ生徒が2023年は15名、2024年は25名、2025年は48名と増えてきています。今年度、48名のうち、31名が3部の生徒たちです。中国語を使う生徒が最も多いそうです。
戸田翔陽高校では増加する生徒に対応するため、多文化共生室を設け、2名の多文化共生推進員さんが相談や日本語指導に当たっています。多文化共生室は月曜から金曜日までの週5日で15時から18時45分までです。2部の生徒は授業終わりに立ち寄り、3部の生徒は授業前に立ち寄ることが多いとのこと。
決まったカリキュラム等はなく、それぞれが日本語検定の受験勉強や学校の課題、推進員さんが用意したプリント等に取り組み、わからないところを推進員さんに聞きます。
学校の定期テスト前になると30名ほどの生徒が訪れることもあるそうです。そうしたときは英語や国語の教員も援助してくれるそうです。この日は3名の生徒が自分で用意した課題に取り組んでいました。
推進員さんは「数学や物理、化学などの教科でわからなかったところを聞かれることもあり、説明できないときもあります。その時は数学や理科の先生にお願いすることもあります。それぞれの母語で書かれた教科書がほしい。日本語では理解が難しくとも、母語であれば理解できるという生徒もいるので」と話していました。
推進員さんは必要があれば随時、生徒の情報共有を担任の先生としていますが、学期ごとに2回ほど担任の先生との情報共有をする時間を設けているそうです。そうした中で、「これまで上手に話していると思っていた生徒が、担任の先生から『日本語の読み書きでつまずいている』という話が出され、びっくりした」との話もありました。

日本語の会話や文法を学ぶ授業も
戸田翔陽高校では日本語基礎と日本語発展というカリキュラムを用意しています。それぞれ2単位です。日本語基礎は主に日常会話の授業で1年生向け、日本語発展は主に文法などの授業で2年生向けです。国語と英語の教員が1年間研修を受けた上で担当しています。
視察したこの日はちょうど日本語発展の授業を行っていました。この日授業では動詞が使役になるとどう変化するのかを学んでいました。非常に難しいと感じました。
校長先生は「来年は3年生向け日本語で表現することを主とするようなカリキュラムをつくることを考えている」と話しておられました。
県教育委員会は「今後も外国にルーツをもつ生徒は増加していくと考えられることから、戸田翔陽高校の実践を他校にも広げていきたい」と話しておられました。