|
1 知事の政治姿勢について
(1)前知事ファミリーによる県政私物化の実態解明について
Q 三期十一年続いた土屋県政が、あのようなみじめな形で崩壊いたしました。
土屋前知事の失脚の原因となった土屋ファミリーによる県政私物化の実態は、驚くべきものでした。
知事は、就任後の記者会見で「臭いものにふたはまずい。
検察の捜査がすべてを決めるわけでもない。行政がどんな形でゆがめられるのかを知ることは必要だ。
内部調査をしつつ、どうしてもクリアにならない点があれば、調査委員会を設置して事実確認をする必要がある」と語っておられます。
県政に対する県民の信頼を回復し、真に清潔、公正な県政を確立するには、土屋ファミリーの県政私物化の実態解明に率先して取り組む必要があると考えますが、知事の決意を改めてお聞きします。
さて、土屋ファミリーによる県政私物化の手口は、整理すると三つに分けられるかと思います。
一つは、長女の市川桃子容疑者が事実上取り仕切っていた財団法人日本さくらの会を利用して、さくらの郷事業や荒川さくらクラブへの補助事業などを立ち上げ、これらの仕事を自分の会社が請け負う形で利益につなげていたことです。
二つ目は、知事の有力後援企業の便宜を図るため、県のくにづくり助成金などを誘導の手段にして、市や町などに後援企業の利益につながる事業を持ち掛けるというものです。
吉田町に前知事の有力後援企業が出資して建設した文書管理庫に通ずる町道整備では、約八千万円の事業費のうち、約三千万円が県のくにづくり助成金やくにづくり貸付金で財源が手当てされました。
また、市川容疑者は、自分が中心になって設立した異業種交流団体新しい日本づくりフォーラム二一の幹事を務めるガラス会社の意向を受けて、同社が開発したガラスボードの売込みに奔走し、寄居町や狭山市などに導入を働き掛けていました。
寄居町では、昨年度約五千万円を予算化して二校に導入しましたが、うち四千万円がくにづくり助成金です。
三つ目は、市川容疑者の夫がデザイナーであるという立場を利用して、県の文化事業やデザイン関連の事業にも関与し、自らの仕事にもつなげていたことです。
県が新宿に開設した情報センター新宿、いわゆる通称埼玉領事館の内装工事では、市川容疑者が深く関与し、内装設計、設備、什器備品一式から職員の制服まで、デザイナーの夫がかかわっていました。
また、市川容疑者は、ドイツのデザイン学校バウハウスを擬した大学の設立構想を県に働き掛け、市川容疑者の友人である文化人らを委員とする彩の国文化懇話会を設置させ、懇話会やシンポジウムを実施させるなどしていました。
こうした一連の手口を見るにつけても、知事が言うように、行政がどんな形でゆがめられたのか、その原因や背景を徹底的に明らかにし、教訓をくみ出すことが必要です。
そのためにも、この問題で調査委員会を設置するだけでなく、職場討議を起こし、教訓を明らかにすることが大事ではないでしょうか。知事の見解を求めます。
A 上田 清司知事 まず、「知事の政治姿勢について」のお尋ねであります、「前知事ファミリーによる県政私物化の実態解明について」でございますが、この件につきましては、前知事時代の6月に全庁的な調査を行ったと聞いております。
その調査は、「前知事の長女による県行政への強要はなかったか」という聞き方であったと聞いております。
これでは当然「なかった」という結果になると私は思います。
調査では、「強要を感じさせる問い合わせやサジェスチョン、あるいは暗示などがなかったかどうか」を聞くべきであったのではないかと私は思います。
その上で、なぜ、そうなったか原因究明をしっかり行い、今後の県政推進に当たっての反省材料にし、職員の意識改革や自浄能力の発揮に役立てることが必要であると思います。
私は、具体的に事業を絞って、そうした観点から調査することが必要と思っております。
しかし、どのような調査を行えば、最も事実関係が把握できるかについては、もう少し時間をいただきたいと思っております。
慎重に検討を進めて行きたいと思います。御理解ください。
Q 再質問 最初に、前知事ファミリーによる県政私物化についてですけれども、この不祥事に対する県民の怒りは強く、新知事によってその全貌を明らかにし、二度とこのような不正が起きないよう徹底調査がされるだろうことを県民は期待しております。
県政への信頼回復のためにも、強い決意を持って取り組むべきであります。
しかし、先ほどの知事の答弁では、調査委員会をつくるかどうか明確ではありませんでした。
そこで、調査のために、外部の人も含めて調査委員会をつくる考えはないのかどうか、明らかにしていただきたいのです。
また、調査の時期はいつまでと考えているのでしょうか。
私は、少なくとも今年度中に調査結果をまとめ、調査結果については、職員のプライバシーに配慮しつつ、その内容を公開すべきと考えますが、見解を伺います。
A 上田 清司知事 まず、「知事の政治姿勢について」のお尋ねのうち、「調査委員会の設置は、いつ頃になるのか」及び「いつ頃までに調査するのか」についてでございますが、私は、まずは内部調査だと思っています。
この調査で、明らかにならない場合は、調査委員会の設置も考えたいと思いますが、まずは内部調査、まだ、時期や方法については、私も就任したてでございますので、少し時間をかけて研究したいと思っておりますので、お許しをいただきたいと思います。
次に、「調査結果を公開すべきではないか」についてでございますが、職員のプライバシーの問題に十分配慮して、公表することを前提に考えております。
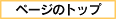
(2)企業献金について
Q 知事は、マニフェストの中で「埼玉県取引企業からの献金は受け取りません」と公約されています。
現行法でも、政党や政治資金団体以外の政治団体に対する企業献金は禁止されておりますが、知事があえて「埼玉県と取引関係にある企業からの」と限定を加えたのは、いかなる理由に基づくものでしょうか。
また、政治資金パーティーなら、企業のパーティー券購入も認めるという立場でしょうか、明確にお答えください。
改めて指摘するまでもなく、我が国の政治をゆがめ、政治腐敗を生み出す大もとになっているのが企業・団体献金です。
今回の土屋ファミリー疑惑でも、土屋前知事の資金管理団体に対する企業献金をめぐる不正経理が捜査の対象となりました。
私ども日本共産党は、政党や政治家の政治活動というのは、主権者である国民一人一人の浄財によって賄われるべきであると考えています。
今回の教訓を生かすためにも、知事自身がパーティー券収入も含め企業・団体献金を一切受け取らないだけでなく、企業・団体献金を全面的に禁止するよう関係法令の改正を強く国に要請すべきと考えますが、併せて知事の見解を求めるものです。
A 上田 清司知事 「企業献金」のお尋ねのうち、マニフェストであえて「埼玉県と取引関係のある企業からの」と限定し「献金は受け取らない」とした理由についてでございます。
前知事が政治資金規正法に関する事件で辞職されましたので、私は、企業とのしがらみ・癒着をなくし、政治倫理の確立を図るため、政治資金規正法を遵守するという決意を込めて、あえてマニフェストで県民の皆様に約束したところであります。
次に、企業のパーティ券購入についてでございますが、政治資金規正法では、企業が政治資金パーティ券を購入することについて、特に制限をしておりません。
私は、政治資金調達のためのパーティの開催は、控えて参りましたが、今後もそのようにしていきたいというふうに思っております。
次に、企業・団体献金の全面的な禁止のための関係法令の改正を国に要請すべきではないかという点についてでございますが、企業・団体献金につきましては、これまで、企業・団体献金は政治腐敗の温床であり、全面的に禁止すべきだという意見もあり、一方、企業・団体も政治的行為を行う自由を有しており、政治献金もその一環をなす行為であるという意見なども多くの論議があります。
私は、より個人献金にすべきだという意見を持っておりますが、企業・団体献金の全面的な禁止について、私自身が国に要請するつもりはありません。
Q 再質問 知事は、パーティー券については、制限はされていないけれども開催は控えたいということですけれども、パーティーの実態は、事実上企業献金と変わりません。
しがらみ一掃を貫くためには、パーティーは開催しないと言明すべきではないでしょうか。
また、企業・団体献金禁止については、国民的合意が図られていないというふうにお答えになりましたけれども、上田知事自身が企業・団体献金は禁止すべきというお考えはないのでしょうか、明確にお答えください。
A 上田 清司知事 私自身は、個人献金をより重視すべきだと考えておりますが、政治資金規正法では、政党及び政治資金団体に対する企業・団体献金が認められております。
献金を受けた団体はこの法律を遵守し、政治資金を適正に処理し、政治資金の透明化を努めるべきだと思っております。
また、パーティ券でございますが、私は、国会議員として10年間で、後援会主催により在職10周年の記念事業の、会費1万円のパーティを今年の2月に行いましたほかは、行ったことはございません。
今後も、こうしたことについては、極力、控えていきたいと思っております。
(3)情報公開について
Q 知事は、就任早々庁議を公開するなど情報公開に前向きの姿勢を示しておられます。
今回の前知事ファミリー疑惑の経緯に照らしても、県として最終的に意思決定した情報にとどまらず、意思決定の過程に関する情報の公開が強く求められております。
庁内の中で政策決定に至る過程でどのような論議が行われたのか、県民がそうした情報にアクセスできるよう、情報公開制度の一層の充実を求めるものです。
同時に、県民が必要とする情報について、県の側から積極的に情報を提供することも県民参加を保障する上で重要なことではないでしょうか。
岐阜県では、予算の編成過程の情報提供をホームページで行い、予算が決定した後も、要求額と決定額との隔たりなどについても説明がされていると聞いております。
また、三重県などでは、情報提供の推進に関する要綱に基づいて情報提供一覧をホームページ上で公表しているとのことです。
県政が直面している課題や問題を共有し、県民参加による県民に開かれた県政を推進する上で、本県でもこうした取組を検討すべきではないでしょうか。
知事より明確な答弁を求めるものです。
A 上田 清司知事 私は、県民に開かれた公正で透明な県政を推進するため、情報公開を積極的に進めることが重要であると考えています。
結果のみならず、意思決定のプロセスにつきましても可能な限り公開していくことが必要だと考えております。
庁議につきましては、9月2日の就任初日から公開をいたしましたが、その他の会議についても、プライバシーをしっかり守るということを前提に、可能な限り公開をしていきたいと思っております。
また、会議の経過等を文書化し、県広報紙等を広く活用することによりまして、政策決定過程の情報を広く県民に提供するなどは、情報公開制度の一層の充実に必要なことだと思っております。
私は、また、県の保有する情報を、積極的に県民の皆様に提供する仕組みづくりが重要であると考えております。
お話にございました予算編成過程の情報につきましても、いかに提供していくかについて、積極的に検討を進めていきたいと考えております。
さらに、県民がいつでも検索し、閲覧できるホームページのシステムを、平成16年4月稼働に向けて開発してまいります。
こうした総合的な情報提供の仕組みによりまして、より一層開かれた県政を推進できるものと思っております。
2 県政運営の基本方針について
(1)大規模開発計画の見直しについて
Q 今度の知事選では、県政私物化の問題と併せて、大規模開発計画や県の財政問題などに対する各候補の考えが問われました。
そこで第一に、大規模開発計画の見直しについてです。
知事は選挙中、ある新聞社の政策討論会で、「本庄新都心も含めて大型事業構想は、取り巻きによる側近政治の影響を受け、きちっとした評価がないままつくられていった可能性がある。
壊せと言うわけではないが、周辺部分の整備も含めて再検討が必要だ」と述べておられます。
そこで伺いますが、周辺部分の整備も含めて再検討が必要と指摘されている事業は、具体的に何を示されているのでしょうか。
また、知事は本庄新都心開発について計画を抜本的に見直す考えがあるのかどうか、見直すとすれば、どのような角度から見直すのか。
この際、知事の考えを明らかにされたいのです。
私ども日本共産党は、本庄新都心開発については、既に事業に着手している早稲田リサーチパーク地区を除いて事業をいったん白紙に戻し、当面、新幹線駅の駅前広場やこれに通じる幹線道路の整備など最小限の周辺整備にとどめるべきと考えますが、知事はどう考えますか。
また、むさしの研究の郷整備構想などの大型開発についても、抜本的に計画を見直すか中止すべきではないでしょうか。
なお、群馬県の八ッ場ダムについては、昭和六十年当時、総事業費が二千百十億円、本県の負担は三百五十五億円と見積もられていますが、その後見直しされないまま今日に至っています。
しかし、現実には五千億円の事業費がかかるとさえ言われています。
市町村などの水道事業体が供給している水道用水は、この十年ほど年間約九・一億トンでほぼ横ばい状態にあり、これ以上莫大な投資をしてまでダム建設が必要でしょうか。
八ッ場ダムについても事業への参入を見直すべきと考えますが、見解を求めます。
A 上田 清司知事 八ッ場ダム建設事業への参入を見直すべきとのご質問でございますが、本県は、人口の増加に水資源の確保が追い付かず、不安定な状態が続いており、このため、昭和61年3月に県議会の議決をいただき、八ッ場ダムへの参画を決定したところでございます。
現時点におきましても、利根川及び荒川から取水している河川水量の約45パーセントが、河川流量の安定している場合に取水できる、いわゆる暫定水利権によるものであり、この暫定水利権の約半分は八ッ場ダム建設事業に参画することを前提として取得したものであります。
したがいまして、八ッ場ダム建設事業への参画は、本県にとりまして現在及び将来にわたり、県民の安心・安全を確保するうえで、必要なものと考えております。
しかしながら、水資源の確保には多額な費用を要することから、現在、改定作業中の「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」、いわゆるフルプランにおける本県の将来の水需給の見通しを見極めながら、更なる水源の開発については、慎重に対応していきたいと思っております。
Q 再質問 この建設への参加は必要不可欠ということですけれども、暫定水利権がどうのこうのということではなくて、現在水の需要が横ばいで推移しているという現実から出発すべきではありませんか。
首都圏全体ではむしろ水は余っているのが現状です。
しかも、八ッ場ダムの建設には莫大な投資が必要です。
政府は、いまだに昭和六十年当時の見積もりを見直しすることさえしておりません。
本県の負担は、昭和六十年当時の計算で三百五十億円ですけれども、現在ではその二倍の負担になるのが確実です。
費用対効果という点、あるいは環境への負荷という点からも、ダム建設については、改めて事業について事前評価を行うべきではないでしょうか。
改めて知事の見解を求めます。
A 上田 清司知事 現在、県内の水需要を満たすために、日量約220万トンの水利権を確保し、市町村等の水道事業者に給水を行っております。
しかし、このうちの45%にあたる日量約100万トンは、暫定水利権であり、渇水時には取水が制限されるなど、きわめて不安定な状況に置かれております。
現在、滝沢ダムが建設されておりますが、完成し安定化が図れても、なお36%が暫定水利権でありますので、この解決のためにも八ッ場ダムの参画は不可欠なものと考えております。
先に議会にも説明し、議決をいただいているところです。
なお、現在改訂作業中のフルプランにおいて、本県の将来の水需給の見通し作業を進めておりますが、昨年8月に県人口が700万人を超え、未だ増加傾向にあることを踏まえると、将来に向けた安定的な水供給のためにも、八ッ場ダムへの参画は欠かせないものではないかと思います。
(2)少子高齢化対策について
Q 知事は就任のあいさつの中で、生活者主権の埼玉をつくるとして、日本一の子育て、教育、医療、福祉の県づくりを宣言されておられます。
前知事も、日本一という空手形を乱発しましたが、問題は具体的な政策の中身です。
知事は、マニフェストの中で、計画的に保育所を整備し、現在三千人の待機児童を四年間でゼロにする、特別養護老人ホームについても約八千五百床増やし二万床にすることを公約に掲げております。
少子高齢化対策の中でも、保育所の待機児童解消、特別養護老人ホームの待機者解消は緊急の課題だけに、知事は、社会保障を中心にした予算編成に努め、これらの課題に果敢に挑戦されることを期待するものです。
そこで伺いますが、これらの課題をやり遂げるために、民間依存ではなく、公的な施設の整備がこれまで以上に求められていると考えますが、知事はどのような方策を検討されているでしょうか。
また、現行のエンゼルプランや高齢者保健福祉計画の見直しについても当然必要になると考えますが、見解を求めます。
A 上田 清司知事 少子高齢化対策を進めていくためにも、利用者の多様なニーズに応えていくことが必要であり、民間を含めた多様なサービス事業者の参入が不可欠であります。
このため、まず、保育所については、公立・民間立を問わず、保育行政の主体であります市町村の計画を尊重し、整備促進に努めてまいります。
併せて、学校や幼稚園の余裕教室の保育所への転用など、既存施設の有効利用や家庭保育室の設置などを進め、児童の受け入れ枠の一層の拡大を図ります。
また、特別養護老人ホームについては、民間の参入が大幅に進んでおり、現在、県内の183施設のうち民間の施設は171施設を占め、民間によるサービスが定着しております。
私は、民間ができることは民間に任せるという考え方に立ち、介護基盤の整備のための財政的な支援やサービスの質の確保などに努めていきたいと思います。
私がマニフェストで申し上げました、保育所の待機児童の解消や特別養護老人ホーム2万人分の整備と現行の計画との整合性につきましては、まず、エンゼルプランについては、次世代育成支援対策推進法に基づく、新たな「行動計画」として、平成16年度中に策定してまいります。
ゴールドプランにつきましては、国や市町村計画との整合を図る必要があることから、平成18年度からの次期計画の中で整合を図ってまいります。
(3)県財政の立て直しについて
Q 知事は、マニフェストの中で、財政再建プロジェクトチームの提言を受け、予算に占める県債依存度を抑制するとして、今年度一般会計予算における県債依存度二〇パーセントを、四年間で一五パーセント以内に抑制するという公約を掲げておられます。
しかし、新たな財政再建のための行財政プログラムの策定もされていない段階で目標値を掲げるというのは、いささか性急ではないでしょうか。
県財政の危機の背景には、地方債と地方交付税を一体化させた政府による集権的財政システムによる地方財政誘導策があったとはいえ、その直接の要因は、県税収入が停滞しているにもかかわらず、大規模プロジェクトを中心に政府の景気対策に追随して公共事業を安易に拡大させてきたことにあります。
しかも土屋県政は、こうした財政危機を、教育、福祉分野へのしわ寄せや人員削減など、いわゆる行政リストラによって乗り切りを図ろうとしてきました。
しかし、こうしたやり方は自治体本来の使命を投げ捨てるものです。
知事は、土屋県政が進めてきた行政リストラを踏襲しながら財政の立て直しを図るお考えでしょうか、それとも大型開発や公共事業を抜本的に見直すことで歳出の削減を図る考えなのか、明確にお答えください。
A 上田 清司知事 次に、「県財政の立て直しについて」でございます。
長引く不況や減税の実施などにより、地方財政全体が、大幅な財源不足に陥っております。
本県財政におきましても、厳しい経済情勢の中、県税収入の大幅な回復を見込むことは困難であり、また、財政調整のために活用してきた基金の残高も、平成15年度末の見込みで約390億円にまで落ち込むなど、大変厳しい状況にあります。
そうしたことから、マニフェストの中でも、財政再建プログラムの検討を掲げたところでありますが、本県財政の健全化は私に課せられた重大な使命だという認識を持っております。
当面の取組といたしましては、10月中に民間人等による委員会を設置し、民間人の優れた経営感覚も活かした提言を踏まえ、新たな行財政改革プログラムを策定いたします。
この中で、職員定数の削減、指定出資法人の改革や徹底した事務事業の見直しを行ってまいりますとともに、電子県庁の推進やNPOとの協働などにより、県行政のスリム化、効率化を図ります。
また、大型公共事業においては、民間委員からなる再検討委員会をそれぞれ設置し、様々な角度から検討するとともに、その他の公共事業についても、投資効果の高い箇所への集中投資など、選択と集中の観点から合理的な再配分を図ってまいります。
さらに、職員のコスト意識、経営体としての意識の徹底を図り、財政の健全化に全力で取り組んでまいります。
3 若者の雇用対策について
Q 若者の失業増大が大きな社会問題となっています。
本県の場合、二十二万人いる失業者のうち、実に約半数の十万五千人が十五歳から三十四歳までの若者で占められています。
若者の雇用が悪化したのは九〇年代に入ってからで、とりわけ九〇年代末からは、フリーターと呼ばれる低賃金、不安定雇用が急増し、事態が急速に悪化してきました。
会社訪問で三十社以上回っても内定が出ず、「自分は社会に必要とされていないのではと感じる」、長く厳しい就職活動に疲れ切った学生からは、失望の声が寄せられています。
自分の学んだことを社会に生かしたい、やりがいのある仕事を見つけたいというのは、青年期のだれもが持つ願いであります。
パート、アルバイトで働く若者の約六割が年収百万円未満という低賃金に置かれているという実態には驚かざるを得ません。
県教育局がこのほど発表した平成十四年度高等学校卒業者の進路状況調査速報でも、就職者総数七千七百六十一人に対して、無業者総数もほぼ同数の七千三百四十九人を数え、中でもフリーターが三千八百十九人と無業者数の半数以上を占めています。
政府の国民生活白書でも、弱年の職業能力が高まらなければ日本経済の成長の制約要因になるとし、今後フリーターが増えると日本全体の生産性を押し下げる要因となり、日本経済の成長を阻害するおそれがあると指摘しています。
低賃金と不安定な就労は若者の自立を妨げ、少子化の原因の一つにもなっています。
若者への安定した雇用を増やし、フリーターからの脱出を応援することは、県政にとっても緊急の課題ではないでしょうか。
知事は、このほど発表したマニフェストの中で、一年以内にやる公約として、情報、ITなど新たな分野での雇用の確保を行うことを掲げておりますが、今日の大企業などのリストラを放置したまま、深刻な若者の雇用を確保できるとお考えでしょうか。
企業リストラによる大量解雇やフリーターの急増、新規高卒者の就職難という事態をどのようにとらえ対処されようとされておられるのか、知事の基本的な考えをお聞かせください。
さて、若者の雇用促進に向けた具体的な対策についてです。
彩の国就職支援プラザを利用する相談者の六割以上は、二、三十代で占められています。
フリーターに対する就職相談や就職あっせんは、国のハローワークや有料の民間就職企業で実施していますが、中高年などの求職者の対応で手がいっぱいだと言われています。
そこで提案ですが、第一に、国が検討している若年者ワンストップサービスセンターの設置を図るべきです。
ワンストップサービスセンターは、産業界、教育界、地域社会、行政の連携の場として、若年者が雇用関連サービスを一か所でまとめて受けられるというものです。
経済産業省では、各地の地場企業や医療、介護、保育などの公共サービス分野で求人を掘り起こし、職業訓練の機会を提供するために、全国で十か所程度のセンターにモデル事業の委託が検討されています。
県として、これらの事業を受けられるセンターの設置を図るべきです。
第二に、若者の職業訓練の機会を拡大するために、県の高等技術専門校に夜間コースを設けてはどうでしょうか。
東京都では、通学に便利な駅近くに立地する都立技術専門学校で、介護やOAなど就職率の高いコースに受講希望が殺到しているため、夜間コースを開設しています。
第三に、高卒者を採用する中小企業に対して助成金を交付するなどの雇用誘導策を導入すべきです。
ハローワークでは、フリーターに対して、トライアル雇用として三か月企業で試験的に働いてもらい、賃金の一部を企業に補助するということも行われていますが、鳥取県では高卒者の新規採用に賃金を助成する施策が実施されています。
本県でもこのような取組を検討すべきではないでしょうか。
以上四点について、併せて知事よりお答えください。
A 上田 清司知事 私は、これからの日本社会を担うべき若い人たちが、職業や将来に対する見通しを持たずに自立した生活ができないでいることは、本人にとっても社会全体にとっても重大な損失ではないかと考えます。
若年者の失業率の悪化や、いわゆるフリーターの増加の背景には、若者の就業意識の低下といった側面もございますが、経済の低迷による労働需要の減少や企業活動のコスト削減なども、大きく影響しているものと思われます。
したがいまして、就業構造の変化を踏まえながら、若者の就業意識の醸成や多様な就業支援を行うとともに、情報・IT産業をはじめとした新成長分野における創業や新たな事業展開を支援し、雇用の受け皿を拡大させていくことが大変重要であると認識をしております。
御提案の「若年者ワンストップサービスセンターの設置について」でございますが、企業や学校との連携のもと、若年求職者への就職活動を総合的に支援する拠点を整備することは、若年者の雇用対策にとりましても大変有効であると考えています。
したがいまして、国とも十分連携を図りながら、同センターの設置に向けて検討してまいります。
次に、「県の高等技術専門校に夜間コースを設けてはどうか」ということについてでありますが、若年者の安定した雇用を増やし自立を促すために、職業訓練を行い、就職に結びつけることは重要であります。
現在、高等技術専門校では、主に資格取得など技術向上を図る訓練において夜間コースを実施しておりますが、今後ともITを活用した訓練など夜間コースを含め、訓練の機会の拡大に努めてまいります。
また「高卒者を採用する中小企業に対して助成金を交付するなど、雇用誘導策を導入することについて」でございますが、高卒者を採用する企業に対し賃金の一部を助成することが、採用促進にどれほどの効果があるのかどうかについては必ずしも明確ではありません。
御指摘のございました鳥取県の例などを見守っていきたいと考えます。
Q 再質問 知事は、大変その重要性を認められております。
県の高等技術専門校についても、夜間コースの拡大も検討するということは大変評価できるものです。
けれども、行財政改革プランでは、県内十二校ある高等技術専門校を七校に減らす計画になっております。
今失業が増大し、職業訓練の重要性が増している中で、あえて高等技術専門校を統廃合する必要があるのでしょうか。
むしろ充実こそ求められているのではないでしょうか。
統廃合計画は見直すべきと考えますが、見解を伺います。
A 上田 清司知事 「行革プランの統廃合計画の見直し」について、高等技術専門校の再編整備については、平成14年2月議会で条例改正の議決をいただき、整備を進めているところであります。
再編整備は、専門校の施設やスタッフを集約し、職業訓練の充実を図るとともに、就職支援の機能の強化を図るものであり、今後とも求職者の方々の期待に応えていきたいと考えております。
次に「若者の職業訓練を拡大すべき」につきましては、先ほど答弁いたしましたように夜間コースを含めて職業能力開発の機会の拡大に努めていきます。
4 高齢者医療の充実について
(1)県単独老人医療費助成制度の堅持について
Q 県はこれまで、県民の老後における適切な医療の確保を図り、老人の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的として、国の制度に上乗せして六十八歳、六十九歳の高齢者を対象に医療助成制度を実施してきました。
年間約八万人の県民が給付を受け、県民の健康保持と疾病の早期発見、早期治療に大きな役割を果たしています。
ところが、政府が老人保健制度を改悪したのを口実に、土屋前知事は今年度予算の編成に当たって、来年一月一日から六十八歳になる人から制度を打ち切る方針を明らかにしました。
これにより、実施主体である市町村では独自財政による制度の維持が困難という判断から、制度縮小の方向を検討しているところも少なくないと聞いております。
昨年十月の老人保健制度の改悪により医療費の負担増によって、高齢者は通院回数や検査、薬を減らしたり、食費や生活費を減らしてしのいでいます。
例えば在宅で酸素療法を受け、月二回の往診を受けていた方は、これまでの一か月一千七百円から一万一千九百六十円へと負担がはね上がり、昨年十月から今年七月までに経済的理由で酸素療法を中断した患者さんが全国で二割にも上っています。
県の老人医療費助成制度が廃止されることになれば、六十八歳、六十九歳の医療費は三割負担となります。
まさに、命を削る改悪ではありませんか。
長野県は、一人当たりの老人医療費が全国一低い県として有名です。
その中でも、高齢化率三八パーセントという泰阜村は、福祉医療を徹底し、老人医療の患者負担を、村の診療所に限ってですが月二千円までを限度額としています。
九九年度の数値ですが、埼玉県の一人当たりの医療費が七十四万五千円なのに対し、本県より高齢化率が高い長野県は一人当たり六十四万三千円です。
泰阜村の場合は、一人当たり四十五万円という低さです。
医療費の負担軽減がいかに重要かが、この数値を見ただけでも明らかではないでしょうか。
知事選において、埼玉県保険医協会が行ったアンケートに対して、知事は「県政全体の見直しをする中で、財政状況に着目し、可能であれば存続も検討」と答えておられます。
私どもは制度の存続を求めますが、当面、来年一月からの縮小はとりやめるべきと考えますが、知事の見解を求めるものです。
A 上田 清司知事 急速な高齢化や医療技術の進歩など、医療保険制度を取り巻く社会情勢が大きく変化する中で、昨年10月から実施されました制度改正では、老人医療の受給対象年齢が70歳以上から75歳以上に毎年1歳づつ引き上げられることになりました。
また、県単独の医療費助成制度が発足して30年以上が経過し、男性の平均寿命は、70.1歳から78.3歳に、女性の平均寿命は75.6歳から85.2歳にとそれぞれ大幅に伸びております。
このような状況を踏まえ、国の老人保健制度の補完的役割を担ってまいりました68・69歳を対象とした県単独助成制度につきましても、その見直しを行い、平成16年1月から対象年齢を段階的に引き上げることとしたところであります。
極めて厳しい財政状況の中でございますので、既定方針どおり対応していかざるを得ないと思っております。
Q 再質問 平均寿命が延びたので廃止するかのような御答弁でしたけれども、平均寿命が延びたのは、医学の進歩とともに福祉医療制度が大きく貢献したからではないでしょうか。
そもそも知事は、選挙中にアンケートに答えて「県政全体の見直しをする中で、財政状況に着目して、可能であれば存続も検討」と答えているのです。
県政全体の見直しも済まないうちから、既定方針どおり廃止を打ち出すというのは、県民を欺くことになり、到底納得できません。
県民への公約は守るべきと考えますが、再度御答弁を求めます。
A 上田 清司知事 本県は、高齢者人口の急速な増加が見込まれております。このため、高齢者施策は多岐に渡っているところであります。
これらについて、選択と集中の観点から慎重に検討しました結果、県財政が厳しいこともあり、既定方針どおり対応せざるを得ませんでした。
(2)高齢者医療総合センターの整備について
Q 高齢化社会を迎え、高齢者に特有な疾病の予防・治療から寝たきり防止や健康づくりなど、総合的な医療・保健施策が求められています。
中でも痴呆、尿失禁、転倒、意識の昏迷、寝たきりなど、従来なら医療の対象とされない高齢者特有の病態に対する適切な対応が求められています。
しかし、こうした特性を持つ高齢者には、従来の縦割りの医療システムでは対応できません。
一人で複数の疾患を持つこと、同時に精神機能の低下を伴いやすいこと、症状の現れ方も若い世代と違い、自覚症状のない心筋梗塞など、高齢者の特性に対応するにはどうしてもチーム医療が必要とされています。
県が策定した彩の国五か年計画二一には、高齢社会に対応して、高齢者に特有な疾病の予防や治療から、寝たきり防止、健康づくりなどの生活スタイルの改善まで、医療・福祉が連携して高齢者を総合的に支援する県立あるいは公的な医療センターを整備することが施策として盛り込まれています。
そこで伺いますが、高齢者に安心・安全を保障するためにも、医療・福祉が連携して高齢者を総合的に支援できる高齢者医療総合センターの整備について早急に具体化を図るべきではないでしょうか。知事の見解を求めます。
A 上田 清司知事 多くの県民が長寿を喜びとする社会を築くために、県民の生涯にわたる保健・福祉施策の充実とともに、高齢者医療体制の整備が重要であります。
高齢者のための医療は、「病気になりやすい」、「重症化しやすい」、「寝たきりになりやすい」といった身体的な特性に配慮しなければならず、さらに、いつでもどこでも適切な医療を受けられるよう、身近なところで医療体制が整備されることが不可欠であります。
このため、県におきまして、高齢者の疾病についても的確な診断と治療の機能を備え、医療・福祉が連携し、高齢者を総合的に支援する地域中核病院を、県内9つの二次保健医療圏ごとに整備する計画を推進しているところであります。
お話のございました高齢者医療総合センターにつきましては、こうした地域中核病院の整備と併せて検討を進めさせていただきます。
5 学校施設の耐震診断・耐震化の促進について
Q この夏以降、宮城県、北海道と相次いで大きな地震が発生し、大きな被害が出ています。
宮城県北部連続地震で全壊状態になった河南町の北村小学校は、築後三十年以上たっていましたが、耐震診断がされないままでした。
今年四月一現在の都道府県別の公立小中学校施設の耐震化率を調べたところ、その宮城県でさえ五八・四パーセントなのに対し、本県は四〇・四パーセントと、全国平均の四六・六パーセントにも満たない状況です。
学校の耐震化が進まない原因の一つに、耐震診断のおくれがあります。
同じ首都圏の神奈川県は、耐震化率が七三・三パーセントと全国トップですが、耐震診断率でも八七・一パーセントと群を抜いています。
ところが、本県は神奈川の半分以下の三七・四パーセントの耐震診断率というお寒い状況です。
知事は、開会日の就任あいさつでも、県政運営に当たって「あらゆる行政分野に、安心・安全を確保する思想を貫く」と述べられました。
大変心強いお言葉ですが、県内公立小中学校の耐震化並びに耐震診断のこうした現状をどのようにお考えになりますか。
さて、文部科学省は、同省の協力者会議が学校施設の耐震化を推進するための報告書をまとめたのを受けて、五月から六月にかけて都道府県に対する説明会を開いたと聞いております。
協力者会議の報告には、耐震診断が進まない現状を打開するために、危険校舎を早急に割り出し、危険度の高いものから優先的に改築や耐震補強を行うよう求めています。
耐震化の推進策として、新たに簡易な耐震化優先度調査を実施して、耐震診断をする対象校舎の優先度をはかり、耐震診断に基づいて、倒壊又は大破するおそれのある危険度の高いものから優先的に耐震化事業を行うというものです。
そこで、教育長に伺いますが、文部科学省が全国の市町村の計画を取りまとめたところ、二〇〇五年までに耐震診断率を八五パーセントまで引き上げるとのことですが、計画年度内に確実に終わらせる必要があるのではないでしょうか。
昨年十二月県議会で我が党議員が、第一次診断に県庁のマンパワーの活用を提案したところ、今年度から市町村立小中学校校舎耐震化技術サポート事業が実施され、一定成果を上げていると聞いております。
優先度調査においても県庁のマンパワーの活用を検討すべきではないでしょうか、併せてお答えください。
次に、耐震化の促進ですが、学校施設の耐震改修が進まない要因として、国庫補助率が低く、市町村の財政負担が重いことが挙げられます。
そこで、知事に伺いますが、学校施設の耐震改修に対する国庫補助率の引上げを強く政府に要求すべきではないでしょうか。
同時に、県の震災に強いまちづくり事業補助金をくにづくり助成金から分離し、予算の大幅な増額を図るべきと考えます。見解を求めます。
A 上田 清司知事 私は、県政運営に当たって、安心・安全を確保することを哲学の一つにしております。
学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす学習や生活の場でありますとともに、地震等の災害発生時におきましては、地域住民の緊急的避難場所としての役割を果たしておりますことから、その耐震性を確保することは極めて重要だと思います。
公立小中学校の耐震診断や耐震化は、市町村それぞれの実情により整備が進められておりますが、本県の耐震診断率は、37.4%と、全国平均の35%を上回っているものの、耐震化率は、40.4で、全国平均の46.6を下回っている状態にあり、必ずしも十分ではありません。
埼玉県としましては、子どもたちはもとより、保護者や地域住民の皆様の安心・安全を確保するため、事業主体である市町村のご理解をいただき、学校の安全対策に、より一層取り組んでいただけるよう、教育委員会とも十分連携し、積極的に働きかけるつもりです。
また、耐震改修の実施に当たりましては、多額な財政負担を伴いますことから、今後、様々な機会を捉え、学校施設の耐震化に対する補助制度の拡充などを強く国に訴えてまいります。
また、震災に強いまちづくり助成金についてでございますが、この補助金は、メニュー化された補助事業の中から、市町村が自ら優先順位をつけて要望するくにづくり助成金の1メニューとして平成14年度に創設されたものですが、市町村の小中学校の耐震診断に関する補助申請は、今のところあまり多くはありませんので、今後は、市町村に対して、補助制度を活用しながら積極的に事業化を図っていくように一層働きかけたいと思っております。
稲葉 喜徳教育長 公立小中学校施設の耐震診断は、全国的に進んでいない状況にありますことから、国では、平成15年度から17年度までの3年間を耐震診断の計画年度と定めまして、その促進を図ることとしております。
この耐震診断には、柱や壁から耐震性を評価する第一次診断、コンクリートの強度や鉄筋の量などにより評価する第二次診断などがございます。
本県では、公立小中学校施設の耐震診断率を上げるため、本年度から市町村の要請に基づきまして、教育局内の一級建築士の資格を有する職員を現地に派遣し、技術的な指導や助言を行うなど、第一次診断による耐震診断の促進に努めております。
お尋ねの「耐震診断を計画年度内に確実に終わらせることや、優先度調査においても県庁のマンパワーを活用すること」についてでございますが、優先度調査は、本年度新たに導入された調査方法であり、建物の建築年数や階数などを基に診断しますので、従来の耐震診断よりも、より簡易に耐震化の優先度を調査できるものであります。
県といたしましては、平成17年度までの計画年度内に、この優先度調査を含めた耐震診断が完了するよう市町村に働きかけてまいりますとともに、優先度調査においても、さらに、県庁のマンパワーの活用をするなど、必要な支援をしてまいります。
6 埼玉新都市交通伊奈線「ニューシャトル」の利便向上について
Q ニューシャトルは、開業して今年で二十年になります。
乗降客は年間約一千二百五十万人を数え、地域の交通機関として重要な役割を果たしています。
ニューシャトルの走行路は、東北・上越両新幹線の高架張り出し部分を活用した高架方式のため、ホームの高さはビルの四階部分に相当し、高齢者や体の不自由な方にとって大変利用しづらいものとなっています。
沿線十三駅のうち、エレベーターが設置されているのは上尾市の沼南駅一か所のみで、トイレも現在計画されている三か所を含め七か所のみです。
乗客の利便向上を図り、利用客を増やす上でも、関係市町との協議の下に、各駅にエレベーターやトイレを早急に設置すべきと考えますが、県の方針について伺います。
次に、運賃ですが、ニューシャトルの初乗り運賃は他の私鉄などと比べて高く、その上、通勤通学定期の割引率もJRや私鉄と比べ低くなっています。
ニューシャトルの定期割引率は、通勤で三割、通学で五割ですが、JRや私鉄の割引率並みに通勤で四割ないし五割、通学で七割ないし八割まで引き上げるべきです。
以上の点について、総合政策部長よりお答えください。
A 中村 一巖総合政策部長 県におきましては、誰もが快適に安心して駅を利用できるよう「みんなに親しまれる駅づくり補助金制度」によりまして、駅施設の整備を進める市町村に対し助成し、エレベーターやトイレの整備を支援しております。
埼玉新都市交通の駅につきましては、県の補助制度などを利用し、現在エレベーターが1カ所、トイレが4カ所設置されており、今後さらに、伊奈町の丸山駅を含め3カ所のトイレの整備を予定しております。
県といたしましては、高齢者や障害者の方々をはじめ、埼玉新都市交通の利用者の皆さんが快適で安心して駅を利用できるよう、引き続き、沿線の市町並びに埼玉新都市交通株式会社にエレベーターやトイレなどの施設の整備を働きかけるとともに、整備に対する支援を行ってまいります。
次に、定期券の割引率の引き上げについてでございますが、現在の割引率は通勤定期で3割、通学定期で5割となっておりまして、JRや県内の私鉄の割引率に比べ低くなっております。
現在、埼玉新都市交通の経営状況は、当期利益を上げておりますが、昨今の輸送需要の伸び悩みや、平成16年度からJRや沿線市町に支払う施設使用料が年間で1億円増額されること、さらには、開業20年を経て、安全な輸送を確保するための設備の更新が今後必要になってることなどから、極めて厳しい状況にございまして、経営基盤の確立が喫緊の課題となっております。
このような中、会社におきましては、平成14年度から平成18年度までの中期経営計画を策定し、種々の増客・増収対策に取り組んでいるところでございますので、定期券の割引率を引き上げるべきとのご提言につきましては、具体的な増客・増収対策の中で検討するよう、提起してまいりたいと存じます。
7 市町村合併問題と道州制について
Q 知事は、知事選における新聞社の政策アンケートで、「生活圏が拡大しており、市町村の枠組みを見直す必要があることは自然なこと。しかし、単純な合併だけでなく、広域行政など様々な形態を検討することが必要」と回答しておりますが、今政府が推進している市町村合併について、知事の基本的な見解を明らかにしてください。
今年四月三十日、首相の諮問機関である第二十七次地方制度調査会が中間報告を決定し、首相に提出しました。
中間報告では、最大の焦点だった市町村合併問題について、目標とする人口規模を法律で示すことについては賛否両論併記としたものの、現在の財政上の優遇措置は打ち切り、新法を制定して、知事が合併構想をつくって市町村に勧告、あっせんできるようにするなど、強制的な合併の方向を鮮明にしています。
しかも、その後も合併せずに残る市町村については、大半の権限を都道府県に移す特例的団体制度について検討するとしています。
この中間報告に対しては、全国町村会や全国町村議会議長会の代表などからも批判が相次ぎました。
全国町村会は五月十五日に自民党にあてて、一、合併はあくまでも関係市町村の自主的判断で行われるもので、絶対強制しない、二、合併しないことを理由に財政的なペナルティー措置を絶対に行わない、三、合併推進や今後の地域自治組織の設置に当たっての国や都道府県の関与は、必要な助言や情報の提供などにとどめる、などを内容とする緊急要望を行っております。
また、長野県の田中康夫知事は、特色ある地域づくりを進める意欲ある市町村が、合併を選択せず、独自の地域づくりを行っている場合でも、また、住民の意向を踏まえて自主的に合併を進めていく場合にあっても、それらの取組を尊重して必要な支援を行うというスタンスを県の基本方針として確立しております。
そこで、知事に伺いますが、本県でも市町村合併問題については、市町村の自主的な判断を尊重し、合併を選択せず、自主的な地域づくりを選択した市町村に対しても、県として必要な支援を行っていくという方針を明確にすべきではないでしょうか。
さて、地方制度調査会の中間報告では、都道府県合併の仕組みづくりやその先の道州制移行についても言及しています。
知事は今度の選挙中、「経済振興を考えると、県の力で産業を興したり雇用をつくるのは限界で、道州レベルでないと難しい。県は、国と市町村の間にある中二階のようなもの」と県の役割を否定し、道州制の導入を主張されております。
しかし、広域自治体としての都道府県が我が国の地方自治の進展に果たしてきた役割は極めて大きなものがあります。
自動車公害対策やダイオキシン対策、あるいは福祉医療制度の導入などを見ても、市町村と連携し、国に先んじた施策を次々と展開し、住民の福祉向上と安全の確保に寄与してきたのであります。
そうした都道府県の役割を認めるからこそ、知事も代議士の職をなげうって知事選に立候補されたのではありませんか。
住民自治という視点を忘れ、経済、産業の視点から地方制度を論ずることは、地方自治の否定につながる考えであります。
道州制問題に対しては、団体自治だけでなく、住民自治の尊重という立場から慎重に対応すべきと考えますが、知事の見解を求めます。
A 上田 清司知事 まず、市町村合併についての基本的見解でございます。住民の生活圏の拡大に合わせて、現行の市町村の枠組みを見直していくことは自然な流れだと考えます。また、昨今の厳しい財政状況のもと、市町村は自らの足腰を強化し、自立性を高めていくことが必要であり、自主的な市町村合併は、その有効な手段だと思っております。
そして、市町村合併は、市町村や住民の方々が将来のまちのあり方を検討する中で、自主的な判断のもとに行われるべきであり、強制されることがあってはならないと思います。
こうした中で、県内の多くの市町村が自立を目指し、自主的に市町村合併に取り組んでおります。一方で、合併を選択しなかった市町村につきましても、市町村において自立性を高めていく努力が必要であることは申すまでもありませんが、県として当然、必要な支援をしていかなければならないと考えています。
次に、道州制に対する見解についてでありますが、道州制の必要性について、一つには、生活圏の拡大があります。行政課題も広域化し、ゴミ問題や自動車公害問題などはすでに一つの都県では対応しきれない問題となっております。
一方、国が決めて地方が従うという今までの行政の在り方を変えていくためにも、住民の意思をよりよく反映できる地方が、国に対抗できる力を持つことも必要だと考えています。
こうしたことから、私は、同じ課題を抱える首都圏の都県が一体となり、国の権限、財源の大幅な移譲を受け、自己完結型の行政組織を構築する、いわゆる道州制の導入を視野に入れているわけであります。住民自治を否定するのではなく、むしろ地方分権を強化するための受け皿として、その必要性を認識しているものであります。御理解を賜りたいと思います。 |

